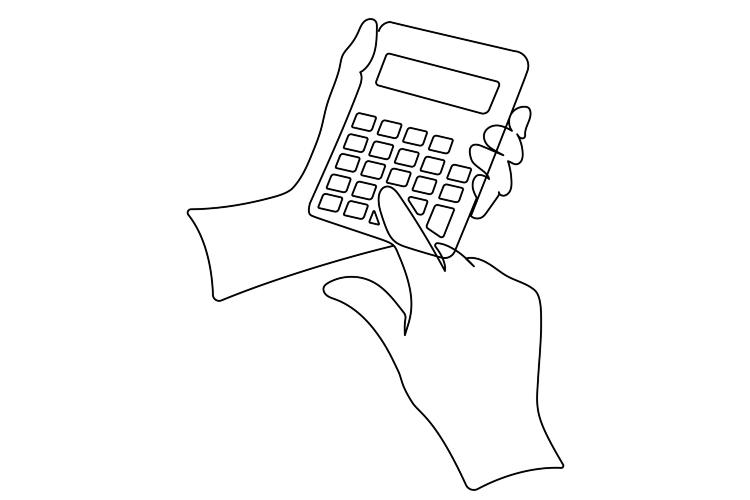目 次


朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す
債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す
1. 法定利率とは?|民法で定められた利率
「法定利率」とは、民法によって定められた利率のことです(民法404条)。お金を支払う側と受け取る側の間で、公平を図るために定められています。
お金の支払いが遅れると、支払う側がそのお金を使える期間が延びる半面、受け取る側はそのお金を使えません。つまり、支払う側が利益を得て、受け取る側は損をするという事態が生じます。
このような場合には、少なくとも法定利率による損害賠償(遅延損害金)を認めることで、お金を支払う側と受け取る側の公平が図られます。
2. 法定利率が適用されるケース
法定利率が適用されるのは、たとえば以下のような場合です。
借金の遅延損害金が発生した
不法行為に基づく損害賠償が発生した
中間利息控除を行う
契約の解除によって代金を返還する
2-1. 借金の遅延損害金が発生した
借金の返済が遅れると、返済期限の翌日から、損害賠償にあたる「遅延損害金」が発生します。借主はお金を貸してくれた側に対し、未払いの元本や利息に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。
遅延損害金の利率は、原則として法定利率によるものとされています。ただし、契約によって法定利率を超える約定利率が定められている場合は、約定利率が適用されます(民法419条1項)。
2-2. 不法行為に基づく損害賠償が発生した
故意または過失により、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。たとえば交通事故を起こした場合や、他人を殴ってけがをさせた場合などには、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
不法行為に基づく損害賠償は、不法行為のときから履行遅滞となり、その日から遅延損害金が発生します。加害者は被害者に対し、損害賠償の元本に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。
不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金の利率も、原則として法定利率によります。
契約によって法定利率を超える約定利率が定められている場合は、約定利率が適用されます(民法419条1項)。ただし、不法行為の当事者間に契約関係が存在するケースは少ないため、法定利率が適用されることが多いです。
2-3. 中間利息控除を行う
将来受け取るべきお金を今受け取る場合は、将来における金額を現在における価値に引き直すために減額するのが一般的です。これを「中間利息控除」と言います。
たとえば、交通事故のけがが完治せず後遺症が残った場合は、加害者に対して逸失利益(=労働能力が失われたことにより、将来得られなくなった収入)の損害賠償を請求できます。逸失利益の損害賠償は、将来分も前倒しで請求するのが通常です。その場合は中間利息控除を行います。
中間利息控除は、法定利率によって割り引く方法で行うのが一般的です。今請求する金額に法定利率による利息を加算していくと、将来受け取るべき金額になるように調整します。
2-4. 契約の解除によって代金を返還する
売買契約に従って買主が売主に代金を支払ったあと、その売買契約が解除された場合には、売主は買主に代金を返還しなければなりません。
契約解除に伴う代金の返還にあたっては、受領のときから返還までの期間に対応する利息を付すものとされています(民法545条2項)。
この場合の利息の利率は、原則として法定利率によります。ただし、買主と売主の契約によって法定利率を超える約定利率が定められている場合は、約定利率が適用されます(民法419条1項)。
3. 法定利率は何%? 変更されることはある?
法定利率は民法の制定以降、長らく年5%とされていました。「年5%」という利率は民法制定当時の市中金利を参考にしたものですが、近年では低金利が定着し、法定利率が市中金利を大きく上回る状態となっていました。
このような状況を是正するため、2020年4月1日に施行された改正民法により、法定利率の抜本的な見直しが行われました。現在の法定利率は年3%で、3年ごとに見直されることになっています。
3-1. 現在の法定利率は年3%
2020年4月1日に改正民法が施行されて以降、法定利率は年3%とされています。従来の年5%から年3%に引き下げられたのは、日本国内の市中金利が低く抑えられている状況を考慮したものです。
3-2. 法定利率が見直される時期|3年ごとに見直される
従来の法定利率は年5%で固定されていましたが、2020年4月1日に施行された改正民法により、法定利率の「変動制」が導入されました。
変動制への移行により、法定利率は3年ごとに見直されることになりました。具体的には、下記の期ごとに法定利率が設定されます。
期間 | 法定利率 | |
|---|---|---|
第1期 | 2020年4月1日~2023年3月31日 | 年3% |
第2期 | 2023年4月1日~2026年3月31日 | 年3% |
第3期 | 2026年4月1日~2029年3月31日 | 年3% |
第4期 | 2029年4月1日~2032年3月31日 | 未定 |
3-3. 法定利率の見直しに関する基準
法定利率が見直されるのは、直近で変動が生じた期と比べて「基準割合」が1%以上変動した場合です。変動分と同じだけ法定利率が上下し、1%未満の端数は切り捨てられます。
「基準割合」とは、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで(60カ月)の短期貸付けの平均利率の平均値を言います。「短期貸付けの平均利率」とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもの)にかかる利率の平均です。
直近で法定利率が変動したのは第1期(2020年4月1日から2023年3月31日、年5%→年3%)で、第1期の基準割合は年0.7%と告示されています。したがって、基準割合が年1.7%以上または年マイナス0.3%以下になった場合に、法定利率が変動することになります。
第2期の基準割合は年0.5%、第3期の基準割合は年0.4%だったため、いずれも法定利率の変動はありませんでした。最近は高金利化の傾向にあるところ、その傾向が続けば、第4期以降に法定利率が変動するかもしれません。
なお、基準割合は各期の初日の1年前までに、法務大臣が官報で告示するものとされています。
3-4. 遅延損害金には、いつの時点の法定利率が適用される?
借金返済を滞納した場合や、不法行為をした場合に発生する遅延損害金については、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率が適用されます(民法419条1項)。
たとえば2019年5月1日(民法改正前)に借りたお金の返済を、2020年5月1日(民法改正後)に初めて滞納したとします。この場合、お金を借りたのは民法改正前ですが、返済を滞納したのは民法改正後なので、適用される法定利率は年3%となります。
4. 法定利率による遅延損害金の計算方法
法定利率による遅延損害金の額は、以下の式によって計算します。
遅延損害金の額=履行遅滞となっている額×法定利率×遅滞日数÷365
たとえば、100万円の借金を一括で返済することを約束していたところ、返済期日に30日遅れたとします。
遅延損害金の額=100万円×3%×30÷365≒2466円
この場合は約2466円の遅延損害金が発生します。


弁護士・司法書士をお探しなら
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」
5. 法定利率よりも約定利率が優先する
当事者間の契約によって「約定利率」が定められている場合は、原則として法定利率ではなく、約定利率が適用されます。
5-1. 約定利率とは
「約定利率」とは、当事者間で契約(合意)によって定める利率のことです。たとえば金銭消費貸借契約(=お金の貸し借りに関する契約)において、遅延損害金を年10%とする旨が定められていれば、年10%が約定利率にあたります。
約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率が適用されます(民法419条1項但し書き)。「契約自由の原則」により、当事者の意思を尊重するのが適切と考えられるためです。
銀行や消費者金融、カード会社などの利用規約などではほとんどの場合、約定利率が定められています。したがって、借金やクレジットカード料金などを滞納した際には、法定利率ではなく約定利率が適用されるケースが大半です。
5-2. 遅延損害金について約定利率を定める契約条項例
遅延損害金についての約定利率は、たとえば以下のような条文によって定められています。
第○条(遅延損害金)
1. 借主が本契約に基づき貸主に対して支払うべき金銭債務の弁済を怠った場合には、借主は貸主に対し、当該未払額に応じて、その支払うべき日(同日を含まない。)から当該未払額の完済に至る日(同日を含む。)までの期間について、年○%の割合で、直ちに遅延損害金を支払うものとする。
2. 前項の遅延損害金は、1年を365日として日割計算により算出し、1円未満の端数は切り捨てる。
5-3. 遅延損害金の約定利率の上限
遅延損害金の約定利率は、高すぎると無効になることがあります。
取引の種類に応じて、遅延損害金の約定利率には上限が定められています。下記の上限を超えると、超過部分の約定利率は無効となり、自動的に上限利率が適用されます。
取引の種類 | 遅延損害金の上限利率 |
|---|---|
①金銭を目的とする消費貸借 ※利息制限法 | (a)営業的金銭消費貸借の場合 年20% ※債権者が業として行うお金の貸し借りのこと。 (例)銀行や消費者金融のローン、
元本の額に応じて以下の利率 10万円未満:年29.2% 10万円以上100万円未満:年26.28% 100万円以上:年21.9% (例)個人間のお金の貸し借りなど |
②個別クレジット | 法定利率(年3%) |
③消費者と事業者が締結する契約 ※消費者契約法 ※①や②など、別の法律で例外が | 年14.6% |
5-4. 約定利率が法外に高いと、契約自体が無効となることがある
上限利率を大幅に超える約定利率が定められている場合は、契約自体が公序良俗違反として無効となる可能性があります(民法90条)。その典型例として挙げられるのが、いわゆる「闇金(ヤミ金)」からの借金です。
闇金は、貸金業の登録を受けることなくお金を貸し付ける営業を行っている違法業者です。年率に換算すると数百%から数千%に相当する、法外な高金利を請求する例がよく見られます。
闇金と締結した金銭消費貸借契約は、公序良俗違反によって無効です。また、闇金が利用者に貸したお金は「不法原因給付」にあたり、利息を含まない元本を含めて一切返済する必要がありません(民法708条)。
ただし、法律上は返済する義務がないとしても、闇金から暴力的な取り立てを受けた結果、それに屈してお金を払ってしまう人が少なくありません。もし闇金からお金を借りてしまったら、速やかに警察へ相談することをお勧めします。
6. 法定利率に関してよくある質問
Q. 法定利率は将来また変わる?
現行民法では、法定利率は3年ごとに見直されることになっています。2029年3月31日までは、現在の年3%が維持されることに決まりました。その後は、市中金利の状況に応じて変動する可能性があります。
Q. 個人間の借金には、法定利率が適用される?
個人間の借金でも、返済を遅滞した場合に発生する遅延損害金には、法定利率が適用されます。ただし、契約によって法定利率を超える約定利率を定めた場合は、約定利率が適用されます。
なお、借金の利息には法定利率が適用されず、契約によって定められた利率が適用されます。
7. まとめ 約定利率が法定利率を超えていて借金滞納が深刻化しそうな際は弁護士などに相談を
民法で定められた法定利率は、借金の返済が遅れた場合に発生する遅延損害金などに適用されます。現行の法定利率は年3%ですが、3年ごとに見直されることになっており、将来的には変動する可能性もあります。
ただし、契約によって法定利率を超える約定利率が定められている場合は、約定利率が適用されます。銀行や消費者金融からの借金、クレジットカード料金などについては約定利率が定められているため、法定利率は適用されません。
約定利率は法定利率よりもかなり高く設定されているため、滞納が続くと遅延損害金がどんどん積み重なってしまいます。返済が難しいなら、早急に債務整理を行いましょう。
弁護士や司法書士に相談すれば、債務整理の適切な進め方をアドバイスしてもらえます。借金滞納が深刻化する前に、早い段階で弁護士や司法書士に相談するのがお勧めです。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)


朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す